~ 先行事例から何がくみ取れるか・ネットワークの構築 ~ 日本語教員研修会(2月23日)報告 No.5 講師 今井武 氏( 公財 石川県国際交流協会 )アンケートへの回答
2024年度 第4回 日本語教員研修会
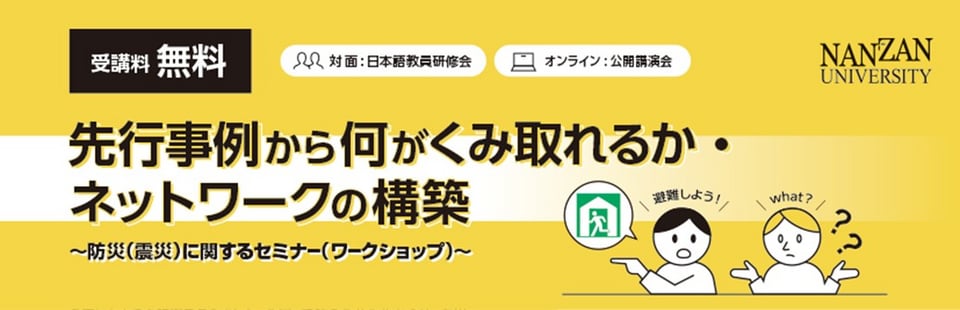
アンケートへの回答
アンケートに寄せられた質問に回答します。
多くのご質問を頂戴しましたので、選定しご紹介いたします。
ご理解のほどよろしくお願いします。
回答者 今井武 氏(公財 石川県国際交流協会 日本語専任講師)
避難所での生活が困ったというお話をいただきましたが、やはり「災害が発生してから避難する」までの行動も外国人にとって大変なところもあったのでしょうか。
いくつかそのようなケースを教えていただきました。ある例では、そもそも地震がどのようなものかを知らず、地震が起きた時にどうすればよいのか、寮に留まるべきか、避難所に行くべきか、そのような基本的な知識も教えてもらっていない人がいました。また別の例では、とにかく被災した建物から外へ逃げたのですが、どこへ避難すべきかわからず、周囲の人に声をかけてもらって、ある場所へ避難、そこで知り合った人から水を分けてもらい、通りかかった人から別な避難先を教えてもらうなど、複数の人の小さな支援が避難につながったことも聞きました。
地震が起きたとき、外国人に関わる団体はどのような初動をすべきでしょうか。
平時から、関わりのある外国人住民に対して防災の情報を提供し、被災時にお互いの情報を確認し合う手段方法を確保しておき、ご自身の動ける範囲で情報収集・提供・物資支援などしていただいてはどうでしょうか。困っている方の情報など国際交流協会など外国人住民支援の拠点に提供いただいてはどうでしょうか。困っている方の情報などを国際交流協会など外国人住民支援の拠点に提供いただくことも大変助かります。
正月で旅行に来ていた方への支援についてお聞きしたいです。
能登半島地震の発災時も観光地などで数日間移動ができなかった方がいらっしゃいました。人が集まりそうな場所に、外国人住民や観光客への情報提供、コミュニケーションのための多言語のツールがあるとよいのではないでしょうか。また、各国大使館の連絡先などを共有しておくと、早めの救助、支援に繋がると思われます。
被災地への立ち入っての支援、救助について
早い時期から支援、救助に入られた機関、団体があったことは承知しています。その方たちの努力や献身には頭が下がります。また、被災地に立ち入らない判断が正しかったのか、どんな課題があったのかも時間をかけて徐々にわかることもあるかと思います。ただ、能登半島の場合、入っていくルートが非常に限られたこと、そのルートでもパンクする車も多く、被災地では車を駐車する場所さえなく、支援者の受入れには非常に困難があったことから、むしろ半島のような地形的特徴のある場所では、そのような立ち入りの困難が起きることを教訓として共有してはどうかと思います。
外国人労働者の受け入れ機関が「水の持ち運び用容器」や非常時用の物を宿舎に備えておくべきだと思うが、そのような受け入れ態勢をとっているところは少ないのか?
支援の体制を全ての受入れ機関がとっていることは理想だと思いますが、就労者の勤務先や管理団体、それぞれで対応に差や違いがあるのが現実と思います。働き先だけではなく、出身国からのサポートや情報提供も異なっていたようです。避難所が誰でも使えること、外国人が行ってもよいことをまず伝えておくことが最低限の支援を受ける可能性を広げることにつながるのではないでしょうか。
石川県の方たちが「やっておけばよかった」と思われることについて、その後どのように実践なさっているのかをお伺いしたいと思います。
県では、「外国人住民と学ぶ防災講座」「災害時語学サポーター育成講座」などを通じて、外国語での情報提供や地域での防災訓練や防災講座を支援しています。
以上


