「日本語教育の参照枠」を活用した授業づくりのためのワークショップ 日本語教員研修会(6月29日)報告 No.3 講師 柏谷涼介 氏( セントラルジャパン日本語学校 )アンケートへの回答
2025年度 日本語教員研修会
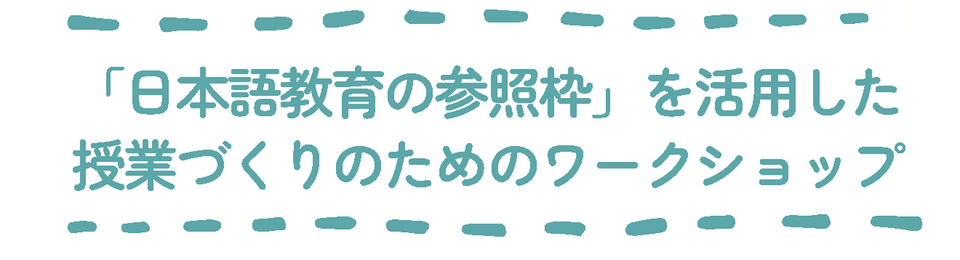
アンケートへの回答
アンケートに寄せられた質問に回答します。
多くのご質問を頂戴しましたので、選定しご紹介いたします。
ご理解のほどよろしくお願いします。
回答者 柏谷涼介 氏(セントラルジャパン日本語学校)
成績をどうするか、評価をどう成績につなげるかを教えていただけるとありがたいです。
日本語学校等の教育機関での成績だと想定するなら、各機関がそれぞれの判断で成績をつければいいのではないかと思います。今回はルーブリックで授業での学習目標の達成度の目安を測る形式で行いましたが、各機関における成績の付け方は各機関で考えるべきだと思いますし、参照枠がそれを規定しているわけではありません。ただ、認定日本語教育機関の認定を想定されているなら、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」の「学習成果の評価」にあるように、いわゆる「テスト」だけでなく、授業の目的に合わせて多様な評価を用いる必要があります。
ワークシートの2)でモジュールを設定する際、2 個選ぶのが適切でしょうか?課題の設定次第では1個の場合や3個の場合も考えられると思います。
はい、状況によっては2つ以上のモジュールを選ぶことになると思います。その中で主要なものを授業活動や評価に使用することになると思います。
ルーブリックで二つの記入例が示されました どちらも 4 段階評価でしたが、4段階の理由がありますか。
特にありません。ただし、3段階以下では、判定がかなり大雑把になってしまうと思います。
参照枠を年間スケジュールやカリキュラムに落とし込むための留意点などが知りたいです。例えばモジュールボックスをどのように当てはめるかなどです。
参照枠やモジュールボックスを年間スケジュールに落とし込む、ということがどのようなことを指すのかは分かりかねますが、まずは各機関や団体の理念と、課程の到達目標を考えて、その上で参照枠やモジュールボックスをヒントを得るための道具として使うのが適当ではないでしょうか。
モジュールボックスは国内の日本語学校のみを想定しているものなのでしょうか。
もともとは国内の留学分野のために作られたものですが、中身は参照枠そのものですので、どのような場合でも使えると思います。10モジュールも含めて、必要なところだけを参照すればいいかと思います。
ルーブリックはどのくらいの数、種類用意して新学期に入りますか。だいたいの目処が知りたいです。
今回のような研修の講師を務められる方は、東海地域にどのくらいいらっしゃるのでしょうか?
今回の講師5人は、昨年度日振協主催で行ったワークショップの講師です。5人のうち、3人が東海地域の機関に所属しています。
今回は【留学】のモジュールボックスでしたが、ほかの分野【就労】【生活】などもあるのでしょうか。あればお教えいただきたいです。
モジュールボックスはもともとは留学分野のために作成したものですが、就労や生活の分野で使えないというわけではありません。あくまで参照枠を編み直し、カテゴリー化したものなので、他の分野で使用する時には、必要のない部分は使わなければいいですし、足りなければ足せばいいと思います。それは参照枠そのものと同じ考えです。
4「課題から学習活動を考える」の項目で評価に関係がありそうなその他の要素というのががありますが、具体的にはどのようなものがありますでしょうか。
例えば、現時点では日本語教育の参照枠に組み込まれていない、CEFR-CVの「仲介」などがあります。その他、各機関、各現場で必要なものがあれば、それを評価すればいいのではないでしょうか。
評価を考える時、Can-do は 1 つの達成目標に付き 1 つずつ考えるべきか、場面でいくつかの出来ることを達成して総合的に出来たかどうか評価すべきなのか、またどちらもか...整理できていません。
1回の授業の目標の達成と、学校であれば学期を通してできるようになったことなど、柔軟に考えればいいのではないでしょうか。まずは、その科目で達成するべき大目標のようなものをCan-doで立てて、それを達成するための小目標のCan-doを各授業で設定する、というような考え方もあるのではないかと思います。
以上


